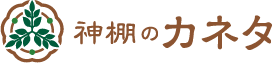初めてのかたへ
-
神棚・神棚板の選び方 神棚は、日々の感謝や願いを神さまに伝えるための大切な場所です。
ご家庭や職場の一角に神さまをお祀りすることで、心に安らぎと清らかさをもたらしてくれます。神棚の種類-
 一社宮(いっしゃぐう) お札が1枚の方向け。最もシンプル。
一社宮(いっしゃぐう) お札が1枚の方向け。最もシンプル。 -
 三社宮(さんしゃぐう) 中央に伊勢神宮、左右に氏神様や崇敬神社のお札を納める定番タイプ。
三社宮(さんしゃぐう) 中央に伊勢神宮、左右に氏神様や崇敬神社のお札を納める定番タイプ。 -
 箱宮タイプ 扉付きでほこりが入りにくく、棚に置いてもOK。
箱宮タイプ 扉付きでほこりが入りにくく、棚に置いてもOK。 -
 コンパクト神棚 コンパクト神棚・御札立て 神具付き
コンパクト神棚 コンパクト神棚・御札立て 神具付き
 設置場所とサイズを確認
設置場所とサイズを確認神棚は目線より高く、清らかな場所に設置するのが理想です。
住宅事情や置き場所に応じて、サイズや取り付け方法を選びましょう。・壁に取り付けるタイプ
・棚の上に置く置き型タイプ
・スペースが限られる方には省スペースタイプも人気※神棚を設置するための棚板も重要です。
・神棚のサイズに合った耐荷重のものを選択
・壁に穴を開けずに設置できるタイプもあります
・板の材質や色合いで全体の印象も考慮素材へのこだわり神棚や神棚板は、長く大切にお祀りするものですから、「どんな木材でできているか」はとても重要なポイントです。材質によって見た目や香り、耐久性、さらにはお部屋の雰囲気にも違いが生まれます。特におすすめなのは、国産の檜(ひのき)です。
檜は古くから神社仏閣にも使用されてきた、日本を代表する高級木材で、神聖な雰囲気を演出するのに最適です。
神棚のカネタでは、厳選した国産木材を使用。職人が一つひとつ丁寧に加工し、素材の風合いを活かした神棚・神棚板をお届けしています。 -
-
購入後のお手入れ方法
-
 お手入れ方法 - 神棚・神棚板 -
お手入れ方法 - 神棚・神棚板 -神棚や神棚板は、日常的に柔らかい布やハタキでほこりを払い、乾拭きすることが基本です。
白木で作られているものが多いため、水拭きや洗剤の使用は避け、木材の変色や変形を防ぎましょう。特に湿気の多い季節は、住宅や部屋によって風通しが悪くカビの生えやすい場所が存在します。除湿剤を近くに置くなどして湿度管理を行い、カビの発生を防止しましょう。 -
 お手入れ方法 - 神具 -
お手入れ方法 - 神具 -神具を掃除する際は、息を吹きかけないように注意し、マスクを着用しましょう。
今でも神事の際は、口に和紙のマスクで行っている神社などがあります。なぜマスクをするのか?これは、人の息が穢れとされるためです。また、陶器製の神具(例:水玉、平次、洗米皿、榊立)は水洗いが可能ですが、木製品(例:折敷、三宝)は水気を嫌うため、必ず乾拭きが基本です。金属製の神具は錆びやすいため、水分をしっかり拭き取り、乾燥させてから元の位置に戻しましょう。
-
-
よくある質問
-
Q 神棚は毎年取り換える必要がありますか?A
毎年取り替える必要はございません。
日々の暮らしの中で、神棚を新たにしたいというお気持ちがあるようであればそのタイミングで行なってください。
ただし、木製であることが多く、経年劣化していきます。そのため、買い替えのサイクルは平均で約5年が一番多いといわれています。 -
Q 神棚の扉から「ギギギ」という音がなります。不良品でしょうか?A
神社の御社は祭典で本殿の御扉(みとびら)を開ける際にこれから神様がお出ましになるという意味で扉から音が鳴るように作られています。
同様に神棚も開閉時に音が鳴るように作られています。 -
Q 神棚を初めて設置するのによい時期はありますか?A
時期に関しての決まりはございません。
家の引っ越しや増改築、お店の開店や事務所開きのタイミングで設置する場合が多いです。
またお日柄を気にする場合は、御神札(おふだ)をお祀りする日にその日を迎えられるようにしましょう。 -
Q 神棚の新調を検討中です。古い神棚はどのようにしますか?A
古くなった神棚は、近くの神社に持参し、お焚き上げしてもらうのが一般的です。多くの神社では「古札納所」を設けており、そこに納めることで適切に処分してもらえます。事前に神社へ確認するのが確実で安心です。
-